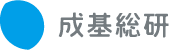シナジーマーケティング株式会社
写真右から
代表取締役社長 奥平 博史 様
経営推進部 向井 理恵 様
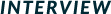
全社で「生成AIの活用を当たり前にする」ために
生成AI導入の動機
■奥平様
数年前から、特にIT企業において、AIテクノロジーの活用は必須となってきています。
しかし、当社の中では生成AIの具体的な導入方法や活用方針、そして、どのように全社に浸透させいくか、明確な判断ができていない状況でした。
2024年度の経営方針の1つに、AI活用を当たり前にするというものがありました。
従来の業務プロセスの効率化からビジネス開発に至るまで、職種や部門を問わず、全ての業務において生成AIの活用を当たり前にしていくことを掲げていました。
まずは、 どうしたら全従業員が安心安全にAI環境を使えるのかというルール決めを行いました。つまり環境整備ですね。次に、多くの従業員がAIをどう使って良いのかがまだわからない状況だったので、各グループ間・チーム間の中の業務プロセスに、生成AIを活用する工程を組み込むという目標設定をしました。
ただ、「AIの勉強をしてください」と一方的に社員に投げかけるだけではなかなか前に進まないので、社内できちんとした教育の仕組みを作って、必要な知識をしっかり身につけてもらう必要があると考えていました。その時に、ちょうど良いご提案をいただけたことが、この取り組みのきっかけとなりました。

全従業員の受講を決定した背景
■奥平様
開発部門では既にAIを開発ツールとして活用する検討を進めていました。一方、業務プロセスなどの改善効果が大きく期待できるのはコンサルタントやセールス部門ではないかという意見もありました。検討の結果、対象人数が多いことからも、セールス・コンサルタントを中心に活用促進をして、全社をリードしてもらいたいという意図もあったり、社内でのAI活用コンテストも企画していたことから、やはりAIの基礎知識は全社員に必要だなと考え、一気に全社の導入を決めましたね。
とにかく2024年度中には、AIを当たり前に活用するという企業文化を定着させ、業務における選択肢として根付かせたいと考えていました。また、この研修を通じてそのカルチャーをしっかり定着させ、1段高いレベルでAIの活用につなげられることを期待しています。
研修を受けての感想
■向井様
導入編はフロントメンバーを中心にAIにあまり馴染みがない従業員が受講したのですが、私含めて研修内容をかなり浸透できたなというか、初心者にもとても分かりやすかったなと思います。全体的に研修内容のレベル感が開発部門を除く当社メンバーと合っていて、もう少し研修のレベルが高いと実用化が難しかっただろうと思います。
導入編では、最初に「AIがなぜ必要か」「なぜ今AIの活用が求められているのか」という話から始まっているので、とても分かりやすく、受けやすい内容でした。

生成AIの社内浸透と活用
■奥平様
間違いなく変化を感じております。浸透活動も少し工夫を入れていまして、役員と部門長を中心に活用事例をちゃんと社内に発信したりしています。 また、そのプロジェクトで動いてるセールスとかコンサルタントのチームの中でも、「活用事例をどんどん社内報みたいな形で出していこう」ということをしております。
毎月アンケートを社内で取っているのですが、研修後は「生成AIは当たり前に使っていくべきなんだ!」という意識の浸透度の高まりを感じました。
■向井様
部署内で言うと、やっぱり壁打ち相手にAI活用していて、 そこで1人で悩むことが結構減ったっていう声はよく聞きます。私自身も実際そうだったりします。
今後の活用方法
■奥平様
いくつかの観点がありますが、業務プロセスにおける抜本的な改革が最も重要なテーマだと考えています。
2024年度を振り返ると、生成AIの活用が着実に広がってきていますね。特に、基本的な情報収集や、企画の初期段階でのアイデア出し、たたき台の作成といった基礎的な業務での活用が、社内に定着してきているように感じています。
引き続き、活用を促進していき、業務プロセスを根本から見直すことで、成果としては生産性の大幅な向上につなげていきたいと考えています。そして、これまで人がやっていた定型的な業務をAIに任せることで負荷を軽減させ、より創造的で本質的な判断が必要な業務にシフトしていきたいと思っています。
あとクリエイティブ業務や開発業務といったところにも、明確に生成AIを組み込んでいくことで、圧倒的な生産性の向上を図っていきたいと思いますね。次のステージとしては、個人の業務改善や部門単位での活用にとどまらず、事業や組織全体で本格的にAIの活用を組み込んでいく必要性を感じています。
研修のおすすめポイントは?
■奥平様
私も実際受講させていただきましたが、「 3つのレベル感に合わせてカリキュラムが構成されている」ことで、レベルに合わせて段階的に学ぶことができました。そして、各前段でちゃんと背景や考え方などのポイントがしっかり押さえられています。もちろん人によっては「もうわかってるよ」っていうこともあるとは思うんですけど、「全社一様にレベルを上げていく際に必要な体系的な知識、情報量」というのが整っているなと思いました。
その上で、導入編、応用編、発展編と上がるにつれて、きちんとワークでは自分で思考して、それを活用していく、という流れになっていました。そして、ワークの後はフィードバックもいただけるというカリキュラムが、これから導入していく企業様に対しては非常に整っていてお勧めできる点だなと感じております。
■向井様
実務でLLM(生成AI)活用できていないと感じる企業にはすごく向いているなと思います。奥平さんが言ってた通りなんですけど、 何が必要かっていう背景から丁寧に説明いただいてるので、非常に入りやすかったです。
プロンプトの書き方も自分なりにできていると思っていたんですが、研修を受けてみるとフレームワークの活用とかさまざまな思考法を使うという認識がなかったことに気付けました。今では研修前の自分では思いつかなかったプロンプトを書くことができているので、そういう点でおすすめです。