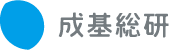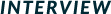
教育コーチング ~本当にお互いを理解し合えるようなコミュニケーション~
所属部署と役職、業務内容
イメージナビ株式会社、代表取締役の中上秀樹と申します。事業としましては、コンテンツ事業、イメージ画像の販売とフォントの販売を行っている事業がまず一つございます。そして、もう1つは、システム開発の部門がございます。
研修を導入した背景・目的、期待していた効果
私たちの会社の事業は2つありますが、それぞれ独立した形で運営をしております。ですので、コミュニケーションの取り方というのも、なかなか北海道の土地柄なのかわからないですけど、うまくコミュニケーションが取れないという課題がまずありました。加えまして、部下の育成や、人材不足ということもあり、「コミュニケーションを図りながら事業を成長させなきゃいけない」という課題もありました。そこをなんとかコミュニケーションをうまくとれるような形で改善していきたいと思いまして、今回研修を導入させていただいたというわけでございます。
研修の中身やカリキュラムで特に印象に残ってる部分や難易度
難易度的には大変分かりやすく講師の先生が教えてくださいますので、すごく理解しやすいです。カリキュラムやテキストの内容も同様です。毎回、次回までの宿題という形でお題を渡されて、部下に話を聞きながらとか、また部下は上長に聞きながらとか、その課題に取り組んでいくということがあったんですけど、そういうやり方もすごくいいなと思いました。また、研修中には、グループでコミュニケーションを取ったり、細かいグループに分かれてディスカッションをする機会もありまして、私が部下と話をしたり、他の会社の社長とコミュニケーションを取ったり、そういったコミュニケーションの取り方でも新しい発見もあり、非常に参考になったし、勉強になったなと思います。
教育コーチングに関する知識やスキルにおける変化
やっぱり、社員の話をよく聞くというところは変わったなと思います。昔はそれほど社員の話を聞くという部分があまりなかったんですけど、最近は「傾聴する」ということ、本当にお互いを理解し合えるようなコミュニケーションを取るということを心がけるようになったなと特に感じています。
実際にどのような場面で教育コーチングを実践されているか
実際、会議の場所とかですね。最初に少し雑談から入って和ましたりとか、休憩所とかで会って話をする時に、相手の話をまず聞くところから始めるとかですね、そういったところを実践しています。
実践していく中で、どのような変化があったか
コミュニケーションはとれるようになったと思います。部下からは、私は社長なのでなかなか話しにくいというところもまだあったんですが、その上でコミュニケーションを取ることによって部下から話かけてきてくれる、ということも増えてきました。そういった意味で変化があったと思います。

組織全体に与えたインパクト・影響
中上様:業務インパクトでいいますと、コミュニケーションが取れるようになったことがすごく大きかったですね。課題が発生したときに、こちらの把握するスピードが上がったと思いますね。
インタビュアー:その把握スピードが上がることによって、例えば業務効率化が起こったり、早めの初期対応ができたりとかしているわけですね。
中上様:そのへんの対応スピードが上がったというのは、やはりコミュニケーションが密に取れるようになったことから生まれてきていると思いましたね。
教育コーチングを活用したさらなる業務改善や新しい活用法
今は、私たち幹部のレイヤーに教育コーチングを受けさせていただいたので、その下のレイヤーまで浸透させる必要があるのかなと思います。受けた教育、教えていただいた内容をもとに、今度は部下の育成のところに役立てていきたいと思いますし、そこでも生かせるのかなと思います。
他社へのおすすめポイント
コミュニケーションの取り方のところのですね、「傾聴して、話をよく聴く、聴けるようになる、そしてこちらの意見もしっかりと伝える」というところが改善できます。そういった意味では、怒りなどのコントロールにも対応できていくと思います。自分をコントロールできるようになるということは、管理者・特に上席の人には必要だと思います。対応できていない企業さんはこの研修を受けることによって、自分のコントロールをしながら相手も(自分自身を)コントロールしていくというような社風というか、会社全体の流れになっていけるかなと思いますね。
インタビュアー:まさに「自立」と「自律」の両方みたいな感じですね。
いいヒントをいただきました!
ありがとうございます 。