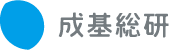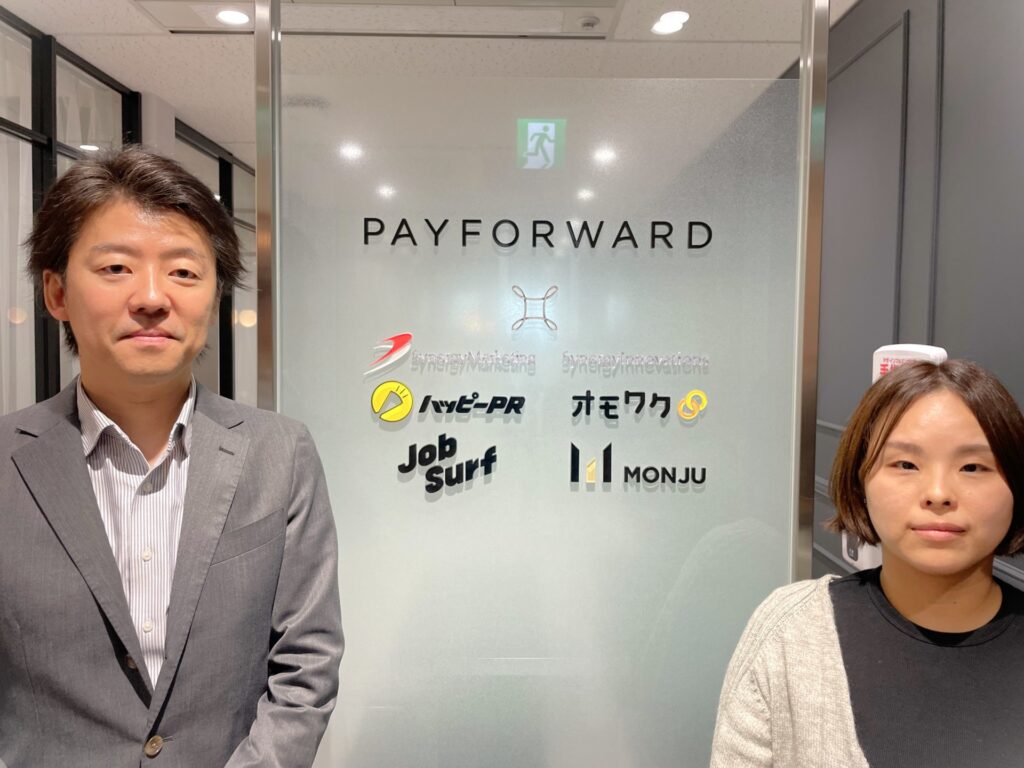ニーズシェア株式会社
総務部 部長
岡本 正子 様
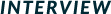
「生成AIを活用するのが当たり前」という文化を作れた
役職および業務内容
所属は総務部になります。総務の仕事の中でも、人事に関することを主に担当しております。仕事の内容としましては、採用活動が1番メインの仕事になっています。あとは社員の研修を企画や、会社の決まり事の社員への周知、会議の運営なども行っています。
研修前の生成AI活用状況
研修前は「一部の社員が使っているかな」くらいのレベルでした。
弊社はシステム開発をやっている会社でして、やはり「生成AIが世の中で流行っている」とか、「生成AIを活用して製品ができている」などの情報は耳に入ってきてはいたんです。しかし、「本当に生成AIを業務に取り入れて作業効率を図ってもいいものか?」という葛藤がありました。社内でもかなり議論はしていたんです。
葛藤の理由の1つが、「考える力が衰えてしまうんではないか」という先入観というか、漠然とした不安みたいなものがありました。社内的には「使っていいよ」と公には言ってはいなかったんですよ。しかし、世の中の流れであったり、実際に生成AIが日本語にものすごく対応しているということで、いろいろ議論した結果、「生成AIを使わない手はない」と、使う方向に会社としては判断したんです。
けれども、間違えた使い方をしてしまったり、LLMからの回答が正しいのかどうか判断できなかったり、ということがあれば、かえって悪影響になるということが分かっていたので、全員の生成AIリテラシーを上げて、「これで使っていいよ」と言えるレベルまで全社をあげて学ぼうと決断しました。
研修受講による効果(前述の課題に対して)
そもそも、LLMであるChatGPTと、GoogleやEdgeとの違いにすら、気付いていない社員もいました。実は、私もわかってなかったんです…。だから、「対話して、自分が欲しい回答を得る、というやり取りをChatGPTとしていかなければいけないんだ」ということを最初に学べました。
また、従来はGoogleなどの検索サイトで情報をたくさん集め、その中から自分で必要な情報を選択して答えを出していたので、結構時間がかかっていたんですね。しかし、ChatGPTは一瞬で「調べて、まとめて、文字にしてくれる」ので、ほとんど時間をかけずに済むので、かなりの生産性向上につながっているなと思います。

生成AIの社内活用・導入状況
研修前は、会社として生成AIの使用を公には許可していなかったんですが、研修を受けることで社内でも大々的に許可を出して、全社で生成AIをどんどん業務に活かしていこうとなりました。全体的にはChatGPTが1番人気がありますけれども、プログラミングをしている社員はそっちに特化したものであったり、絵が欲しい社員がいると絵を作ってくれる画像系の生成AIだったり、みんなさまざまな種類の生成AIをうまく使い分けているようです。そのため、「これを使いなさい」という指示はしていないですね。ちなみに私はChatGPTが相性が合うので、気に入って毎日使っています。
社員同士の会話でもですね、「自分で生成AIに質問すれば一次回答を得られるよね」というレベルの質問をしてきた場合は、「おいおい。ChatGPTに最初に聞いてきたの?」みたいな会話が社内のあちこちで聞こえています。「最初にどこから手つけたらいいのかわからない」などは、日々あると思うんですけれども、気軽な相談役として、まず人に尋ねる前に自分でちょっとChatGPTに聞いてみよう、というのが当たり前になりました。とにかく生成AIを使うことで、「最初の一歩ができる何かを導き出してもらおう」という動きが社内全体に浸透してきたなと実感しています。
研修の中身について
私も3ヶ月にわたってしっかり研修を受けさせていただきました。自分自身、ChatGPTをGoogleだと思ってるぐらい勘違いしていたので、本当に導入編から、衝撃を受けておりました。「え?会話ができるの?」というように、最初から驚きばかりでした。
総務では、文章作成の依頼がよく来ます。今まではあちこちのサイトを見て、様式やテンプレートを集めてきて、それを自分で要約したり切り貼りして、自社用のものを作る、という作業だったので、数時間はかかっていました。
しかし、ChatGPTに「こういう様式でこんな案内作るとしたらどんな感じ?」と友達に聞くような感覚で聞いてみると、さらさらさらっと一瞬で出てきたんです。ちょっと違うなと思った時も、「この辺をもうちょっとこういうふうにしてくれると良いんだけど」という感じでプロンプトに打つと、これまたすぐに修正してくれます。しかも、修正部分はなぜそのように修正したのかまで教えてくれるんですね。
本当に優秀なアシスタントができたと感じています。今まで数時間かけて作っていたものが、ChatGPTを使うと20分で完成したという、素晴らしい成功体験を得てからは、「もう生成AIを使わない日はない」という状態ですね。
研修プログラムの推しポイント
工夫したプロンプトでChatGPTに指示することで、自分が欲しい回答がもらいやすくなるので、プロンプトの書き方の練習をたくさん行いました。正しいプロンプトを作成できなければ、いくらChatGPTが目の前にあっても活用できません。ですので、何回も何パターンも、実際に手動かしながら考えるワークがあったおかげで、いろんな状況や条件下で、どのようなプロンプトが適しているのかを、かなり叩き込まれました。そこで学んだことを応用していくことで、実際に仕事で役に立っているなと実感しています。
きちんと基本的なところから押さえながらレベルが上がっていくので、全く生成AIを使ったことがない人でも、3ヶ月後にはかなり使いこなして、自分の業務に役立てることができていると思います。また、生成AIを利用するだけではなく、実際に生成AIを使って課題を解決するために必要な「ビジネス思考」についても研修内容に含まれています。だから、本当の意味での課題解決のための経験値が上がる感覚もあり、将来的にも非常に役立つものだと感じています。
全社導入したことで得られた成果
メリットとしては、やはり全員が「AIのリテラシーを持って、AIを活用することで生産性を上げる」、もっと優しい言葉で言えば、「自分の仕事を楽にする」とか、「早く終わって自分の時間をたくさん取れるようにする」とかに直結するということですね。そういう目的意識を持って研修を受けてもらっているので、「触らず嫌い」だった社員の多くが、研修を通して必然的に生成AIを知ることによって、自分の仕事にどれだけ役に立つかと気づけたので、作業効率も上がっていると思っています。
また、会社自身として初めて、全員で同じ研修を受講しました。すると、社内で「ここは結構手を使うからパソコンでやったほうがいいよ」とか、「ちょっとChatGPTに聞いてみたよ」などと、全員が生成AIの話ばっかりしているような時期もあり、一体化を感じられたのが嬉しかったです。研修を通して、生成AIを当たり前に使っていく文化ができたと思っています。

研修後の具体的な生成AIの活用法
技術者職では、プログラムを生成AIに書かせていたり、書いたコードをチェックしてもらったりという社員が、すでにたくさんおります。
私自身、総務での採用や人事の仕事では、人のフォローに使っています。例えば、相談されたときに、それに対する自分の回答があっているのかをChatGPTに相談して、上手い言い方がないのかや、その人が今どんな心理状態にいるのかなども、自分の頭で考えるだけでなく、多面的に教えてもらえるので、いろんな気づきを得られます。今までより、社員のサポートがスムーズに、かつ自信を持ってできるようになりました。
人材育成領域における活用
先ほども述べたように、人材育成領域に、生成AIはかなり使えるんじゃないかと思っています。心理学的な知識などを、全く専門ではない私にも分かるように、優しく説明してくれるからです。本当に相棒のように、毎日相談事を投げてアドバイスをもらって、という使い方をしています。ぜひ皆さんにも、人との関わりで生成AIを活かすことをお勧めします。