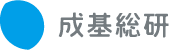ユーミーコーポレーション株式会社
建築事業本部 常務取締役 熊本支店長 一級建築士
奈良崎 稔 様
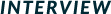
AI活用を通じて、「ユーティリティな人材」の育成へ
研修のオススメポイント
一番は、内容が面白く、非常に分かりやすかったことです。
また、構成的に1つ1つが短かったので、受講者側からして、とても入りやすかったです。従業員からも短時間の動画が多いことで、隙間時間でも取り組みやすかったという意見が上がっていました。
さらに、合間合間にあるLLMを使って行うワークについて、実際にやってみて「できた!こういうことか!」というのを実感しやすかったことが良かったです。実際に50代の社員からも、「結構興味深いです」と僕に積極的に報告しに来てくれていたので、年代関係なく学びやすいと感じました。いろいろな業種の企業さんでも、導入すれば結果は生まれてくると思います。
研修受講後の変化
私自身も研修を受けましたが、取締役であり熊本支店長として、自社の従業員たちにどんな変化があったかを中心にお答えします。
今までは、自分で本を買って読んで、その知識をもとに、「営業の時はお客さんごとにどんな切り口がいいのか」とか、自分の仕事の進め方を頭に貯めていって、というのが多かったと思います。しかし、今はいちいち本を読まなくても、むしろ本を読むより分かりやすく、LLMが知りたいことを教えてくれます。それをまとめれば『自分の業務に関する教科書』をいとも簡単に作ることもできます。この前は研修を受けた女性スタッフが、ChatGPTを使ってイベントの企画書を出してきたんです。業務の効率化はもちろんのこと、質的な変化まで起こっているのを感じます。
企画立案もとても簡単になりましたよね。企画書の作成もChatGPTが手伝ってくれるから、みんなのやる気が以前より上がっていることを感じます。仕事の仕方も、振り返ると本当に無駄な時間が多かったんだと分かりました。単純に部下がChatGPTを使ったら、優秀な部下が一人増えたようなもので、部下が2倍になった感覚です。
今までは何か新しいことをやるときも「え~」っていう反応だったのが、ChatGPTを使い始めた今では「いいですよ、やってみましょう」と変わっています。特に、全体的に新しいことへのハードルが下がって、専門外のことでも挑戦がしやすくなったと思います。

効果的だと感じた、LLMの活用法
今まで文句を言っていた部下が、だんだん文句を言わずにバンバン仕事を進めてくれるようになってきたんですよ。様子を聞いてみると、面白いLLMの活用をしていました。
例えば「稟議書の作成」です。上司の意向と合わずに、よく稟議書を却下されていた際に、ChatGPTに上司の性格とか全部打ち込んで、「この人に気に入ってもらえるような稟議書を作って!」とプロンプトに入れたそうです。そして、その稟議書を提出すると、例の上司がとても喜んだらしくて(笑)
却下したり、修正させるのにも労力がかかるので、上司も部下も楽になって、双方Win-Winの状態が作れました。それは稟議書に限らず、いろんなところで使えると思っています。
例えば、営業でもお客さんの人格を全部作ってプロンプトに含んだ状態で、「この人に合う営業の切り口を考えて!」とやってみたんです。最初は面白いなと思っていただけだったんですが、なんと実践したら成功することが多かったんですよ。
受講者の進捗の確認について
進捗率が確認できるので、例えば進捗が0%の人を赤色にして、役員・上司も含めて参加者全員に共有をしていました。昭和の頃だと、クラスの成績表が貼り出されるじゃないですか。あれに近い状態で参加者を一覧化しました。例えば、受講期間が残り半分になったら「進捗率30%以下の人を赤色にして」という感じで追いかけをしました。
人によっては、期限ギリギリに怒られながら受講を終えたタイプもいれば、計画的にやる人もいましたね。研修に強い興味を持って、ゲームで次のステージにどんどん進んでいくように、「次は?次は?」と、かなりのスピードで進めている人もいました。スマートフォンでも受講できるのも、若い人にとってはYoutubeなんかと同じ感覚で、全然抵抗なく見られたようです。やっぱりEラーニングという形式で、自分のペースで受けられて、かつその状況もこちらはしっかりと確認できる、というのが良いなと思いました。
会社全体で研修を受講する必要性
私自身は、昔から「何でそんなアイデアが湧いてくるんですか」って言われるくらい、企画立案やアイデア出しが得意でした。でも、生成AI を使えば一発で自分が考えるよりいろんなアイデアを一瞬で出してくれるようになってしまいました。私からすると、AIは敵かもしれませんね(笑)でもそれだけ生成AIが、その業務の経験値がある人と同じくらいの業務を遂行できる、ということです。だから、生成AIを社内全体に広めるかどうかが、かなり重要だと思います。生産性が明確に変わってくるからです。若い社員たちは、目を輝かせて研修を受けた後もガンガン生成AIを使っています。「生成AIという言葉に漠然とした抵抗感がある」という理由で取り入れていない会社は本当にもったいないと思います。
一部の人だけが生成AIを使ってますよという会社は多いと思います。しかし、一部の生成AIに精通した人がいても、強い目的意識をもって「いつ・何を・どの順序で・どれくらい深く」他の社員に伝えるかを考え、教えてもらう側の準備も整えないと、社内で生成AIの知識を広めることはほぼ不可能です。同じ知識を持っていれば、生産性をかなりあげることができるのに、周りの人はそんなことには気づかないから、学ぶ意欲もないのです。その状態は本当にもったいないと思います。
やっぱりその状況を打破するためにはトップが動くということが大切であると思うので、私の支店では、成基総研の生成AI活用研修を全従業員に受講させ、生成AIを活用して取り組む課題を出しました。

組織全体へのインパクト
研修で学んだだけにならないように、社員にどんどん課題を与えています。
例えば、「フランチャイズの入居率について、目標数値に向かっていくためにどんな施策をとるべきか」を、生成AIを活用して、部署関係なく全社員に提出させました。
これはやってみることが非常に大切で、提出された施策を見てみると、内容が似ているものもあるけれど、そこからさらにプロンプトを自分で考えて次の展開を考えてみたり、さらに新たな疑問や条件を投げかけてみたりなどを、今からみんな覚えていくと思います。
また、今回は不動産のことで生成AIを使いましたが、これからは建築や営業など、違う部署のやるべきことや実際にどう行動するかなどを、全社員に考えさせていくつもりです。そうすることで自然と、各部の悩みや普段の業務、今後どんな施策をとるべきかなどが分かり、全体で共有できるようになるんですね。いまどき縦割りではダメで、これからは他の部署のことも分かる「ユーティリティな人材」が絶対に必要になってくると思うんですよ。そういう人材は自分のことだけでなく、全体を巻き込んで良い影響を与えてくれますからね。
研修の中でいろんなケーススタディがありましたが、そのおかげで全社員が実際の業務でChatGPTを使える状態になったので、その機会をくださって本当にありがたかったです。ChatGPTを使えることによって、こうしてみんなが肩の力を抜いて、他部署のことも考えられる状態になったと思うので。
AI活用を通じて実現したい、会社の未来像
先ほども述べたように、縦割りをなくして、「ユーティリティな人材」を作ることが今から社会で生き抜くためには絶対に必要だと思っています。そのために、他部署のことも考えさせる機会を作りたいわけです。
巷でよく「副業をしろ」っていうじゃないですか。でも、それって社内でもできると思うんですよ。例えば、管理部でもお客様や土地を見つけてくれば、不動産や営業と同じようなフィーをもらえるなどの、会社内副業が成立するわけです。すると、管理部にいる人はコンビニでバイトするよりも、営業や不動産の勉強をした方が、自分の給与だけでなく会社全体の業績も伸びてはるかに良いですよね。それをみんなが理解すれば、素晴らしい組織になると思います。すぐにできることではないですが、少しずつ社内の変化を感じています。これを続けて、よりよい会社になるよう、努めていきたいと思います。