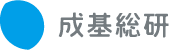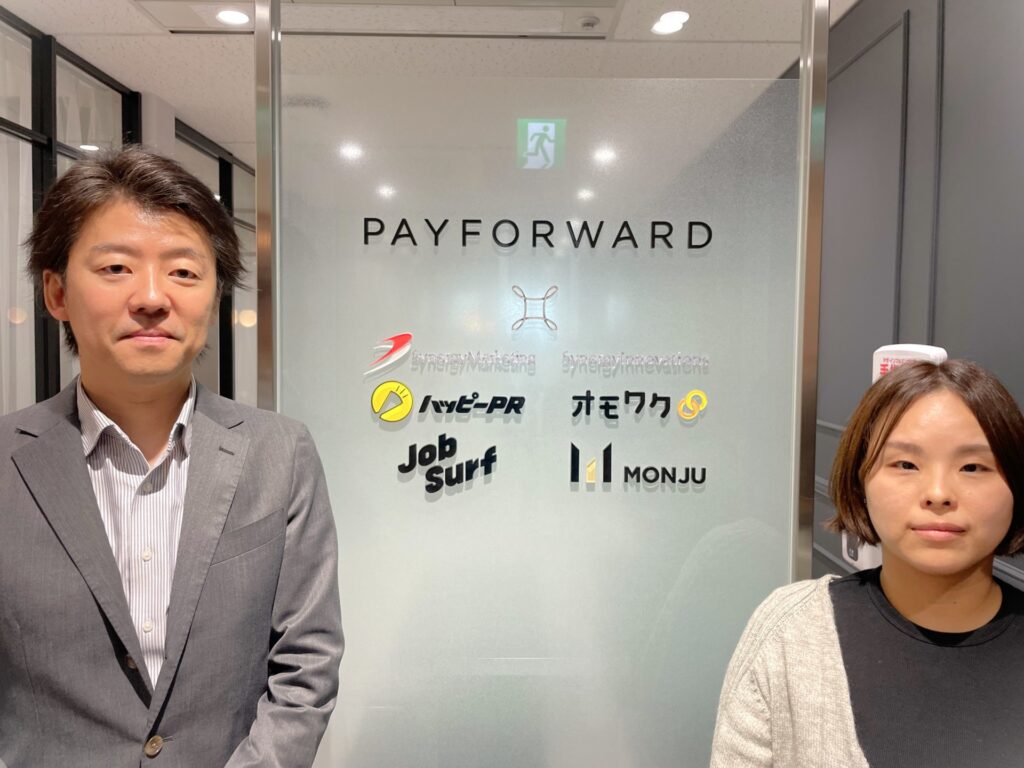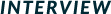
医療現場におけるビジネス思考と生成AI活用
生成AI活用研修を導入した経緯
■安井様
当法人が展開する在宅医療は、病院での診療とは根本的に異なるアプローチを必要とします。病院では、医療者の空間に患者様が訪れ、適切な治療を受ける構造ですが、在宅医療では私たちが患者さんの生活の場に伺います。このように従来の医療の関係性が逆転している環境の中で、どのように医療を活用できると患者さんの人生が豊かになるかを、我々は追求しています。
それぞれの自宅にお伺いする在宅医療では一件一件におけるアプローチが当然変わってきます。柔軟な対応力を身につけることは、在宅医療における「人材育成」の重要な要素であり、我々が大切にしている「人づくり」の根幹でもあります。
そしてその価値観を大切にしながら、「おうちにかえろう。病院」「ごはんがたべたい。歯科」などの事業を展開してきました。それぞれの事業で関わる専門職の種類は異なります。業務内容も違います。しかし、共通しているのは「患者さん、家族にとっての豊かな時間をつくる」というコンセプトを大事にしていることです。そしてそのためにTEAM BLUEでは「医療の質は人の質」を掲げて、ひとづくりに取り組んでいます。
このような背景もあり、TEAM BLUEでは医療機関といえども新たな価値を生み出し続けるためのプロジェクト型の運営が行われています。プロジェクトマネジメントの重要性は高く、生成AIがその支援ツールとして有効であると考えました。スタッフの能力向上のために生成AI活用研修を導入しました。
実際に研修を受けて印象に残っている部分
■安井様
導入編では生成AIの基本的な使い方を学びましたが、その後、MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)やロジックツリーなどのビジネススキルと組み合わせた活用法が示された点が特に有益でした。医療機関では、一般企業ほどビジネス思考に触れる機会が少ないため、こうしたトレーニングを全員で受講できることは非常に有意義であると感じました。

研修受講前後の変化
■安井様
研修を受講したスタッフの間では、「実際に生成AIを活用してみました」という声が増えています。例えば、レポート作成や学会向けの抄録作成において、「生成AIを使うことで迅速に作成できた」という声です。
今後の期待としては、ブレインストーミング(ブレスト)にも活用を広げることです。例えば、MECEを用いたアイデア出しを会議前に生成AIで行うことで、提案の質を向上させることが期待されています。会議にかける前に、「それ一度生成AIとの壁打ちは済んでいるよね?」といったように、「会議前に生成AIを活用してアイデアを整理する」ことを習慣化させていきたいです。初期段階におけるみんなのプロポーザル(提案)のレベルが上がるのではと期待をしています。
今後の生成AIの活用について
■安井様
現在カルテに時系列で入力されている情報を要約し、診療情報提供書の作成に活用することを検討しています。
患者さんは、急性期病院から我々のような地域病院、さらに在宅医療へと移行するため、医療機関同士の情報共有が非常に重要です。現在もFAXによるやり取りが一般的ですが、少しずつ電子化が進んでいます。
生成AIを活用してカルテの情報が項目ごとに分類されるなど自動整理が実現すると、医療従事者の負担が軽減され、患者さんとの対話に充てる時間を増やすことができると考えています。
この取り組みは、医療業界全体にとって大きな変革となる可能性があります。
研修のおすすめポイント
■安井様
生成AIをスタッフ全員の共通言語として活用するためには、一部の人だけではなく、全員が研修を受講することが重要です。プログラム自体が丁寧に設計されており、誰でも一定のレベルに達することができるため、多くの人に適した内容となっています。

生成AI研修受講者の声
受講前の研修への期待と、受講後の感想
■齋藤様
研修前から生成AIを使用した経験はありましたが、独学であったため、正しい活用法を十分に理解できていませんでした。なので研修をきっかけに生成AIをより効果的に活用できるようになったらという期待がありました。
実際に研修を受講したことで、基礎知識が整理され、より効果的に生成AIを活用できるようになった実感があります。生成AIへの関心が一層高まり、日常業務での活用の幅も広がりました。
どのような業務に活用しているか
■齋藤様
研修後、勉強会の案内書作成に生成AIを活用しました。従来は自ら文章を構成していましたが、生成AIを利用することで、プロンプトにキーワードを入力するだけで、簡単に完成度の高い文章を作成できました。
また、勉強会の企画手順を生成AIに入力し、適切な改善点を得るなど、業務効率化に役立てています。さらに、病棟スタッフへの通知文作成にも活用し、文章の明瞭化を図ることもできました。
医療に関する専門知識は持っていますが、イベント企画や基準作成の手順に関しては専門外であるため、生成AIの活用によって、短時間で質の高い成果物を作成できるようになったと実感しています。

実際の業務効率化と今後の生成AIの活用について
■齋藤様
セミナーのアンケート作成など、従来は数時間かかっていた作業が、生成AIを活用することで大幅に短縮されました。医療職は事務作業も多いため、今後は記録作成などにも活用し、効率化を進めていきたいと考えています。
ただし、個人情報の取り扱いには十分な注意が必要であり、適切な管理を徹底することが求められると思います。
研修のおすすめポイントは?
■齋藤様
初心者でも分かりやすいカリキュラムが組まれており、基礎から応用まで体系的に学ぶことができます。演習が豊富であるため、自然に活用スキルが身につく点も魅力です。生成AIをすでに利用している方にとっても、新たな活用方法を学ぶ良い機会となるのではないでしょうか。